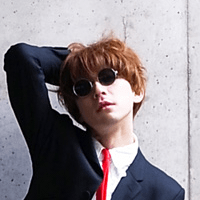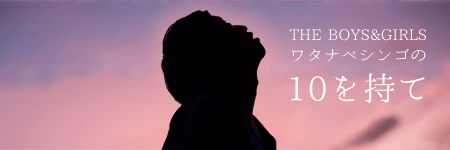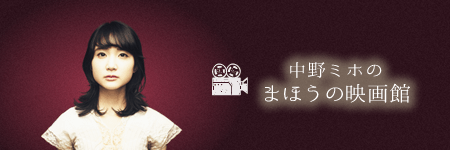平田ぱんだのロックンロールの話
第22話:パンクロック登場!ロックンロールは気合いだ!
おう、おらいはボヘミアンズの平田ぱんだってもんだ
なめてんじゃねえぞ
ああ、今夜のおらいはちょっとばかし荒々しいぜ?
今回のテーマも前回から引き続き
「パンクロック登場!ロックンロールは気合いだ!」
だからな
なにい?
前回も同じテーマだったのにいきなり今回から態度が荒々しくなってわけわかんねえ!
だとう?
なーにそれにはちょいとしたわけがあるだ
前回はおらいはこともあろう事かその日好きになったばかしのロックバンドニューヨークドールズのファーストアルバムを紹介してしまたわけだが、ニューヨークドールズビギナーな上に元々英語が堪能ではないことも手伝って、実はおらいはそのアルバムの一曲目の曲名をおもいっきし読み間違えして、そのまんまで書き記してしまっただ。。オーノー
直してもらおうとも一瞬思ったが、間違えたまんまにしておいた方が「コイツガチでビギナーだったんだな!」っていう説得力、つまるところがリアリティにつながるかな、なんて思惑もちらほら、パンクロックにはリアリティは不可欠だから、結局そのまんまにしておくことにしただぜ。。
ああ、勿論ちょっぴり恥ずかしいぜ?
だからそのことをなんとなく誤摩化したい、というキモチが、今回おらいの文を荒々しくしちまってる、なんて話も。
ふっふっふ、リアリティのためさ
普通のロックンロールとパンクロックの違いはリアリティなんだからな
ロックンロールはどこかファンタジーを売りにするものだが、パンクロックはもっと隣にいるのだ
距離感に限った話をするならばヒップホップとかとの方が括りが一緒なのかもしれないとかなんとか
まあ色々書きたいことはつのるが、この辺で打ち切ろうか
なんせパンクロックの話をせねばならんからな
パンクロックの世間のイメージといえばなんだい?
そう、
「はやい!激しい!わかりやすい!」
だ!!!
倣おうじゃないか
つーことで
ごちゃごちゃうるせえ!
さっさとはじめるぞ!
凄いスピードでいくぜ!
前回から引き続き「パンクロック登場!ロックンロールは気合いだ!」をテーマに掲げ紹介するロックンロールバンドのファーストアルバムは、
コイツだ!!!
ラモーンズ
「ラモーンズの激情」
だ!!!
なめてんじゃねえぞ
まずはロックンロールマナーに基づきジャケの話からさせてもらおうか
一言でいうと四人の男が突っ立てる写真だ
背景の壁はなんか古びたレンガだったり落書き沢山だったりでどうひいき目にみても綺麗ではねえやな
そんな壁と同じような印象の男が四人並んで立っている、いいかえるとその壁とこの上なく似合う四人の男が並んで立っている
しかも正面を向いてだ、わかるか?
何かがはじまってしまいそうな予感、つまるところが期待感、煽られるじゃないか
これほど煽られるジャケも珍しいな、なんの変哲もない写真のはずなのに、、予感と期待の上がりがぱねえ
四人の男の後ろには白文字でバンド名がでかくドンだ
どうだ、まいったか!てな具合にな
必要なものが全て揃っているじゃないか
いらないものが一つもない
かっこいいぜ
このファーストアルバムのジャケだけでラモーンズというバンドの全てが語れると言っても過言じゃあない
ラモーンズとはいらないものが何一つないサウンドを武器にしたロックンロールバンドだからだ
ロックンロールの最大の見所はその節操のなさ、何とでも関係を持ってそこに時に誰も予想だに出来なかった祭を開催してしまうことにあるが、反対に何とでも関係を持つがゆえに余計なもの、全く必要のないものも連れ立ってしまうという罠も潜んでいる
パンクロック登場時の1970年代の世界のロック音楽事情がちょうどその罠にはまっている時分だったらしく、まさにいらないものが多すぎる状態だったらしい
技術や時間や人や金がわんさか必要なキッズから遠く離れた産業と化していたらしい
パンクロックとはそんな歴史の必然で登場したものらしい
まあそんなしゃらくせえ話はこれからする話とまるで相容れねえな
ロックの歴史本でも読んでくれ
いくらでもあるだろ
おらいがしたい話はそんなもんじゃない
おらいが話したい話はあくまでラモーンズのファーストアルバム「ラモーンズの激情」のジャケに対するトークだ
重要なんだ
まずこの四人の若者のファッションに関する話をしよう
ここだけの話ロックンロールはファッションだからな
パンクロックは特にそうだ
服装見た目を重視していないパンクバンドはクソだ
絶対に信用するな
それは別にド派手な格好をしているかどうか、なんてチャチな話じゃねえ
こだわり、そうこれはこだわりに関する事なんだ
ラモーンズは全員こだわっている!
全員長髪革ジャンジーパン、そしてスニーカーだ!
ラモーンズが解散まで守ったファッションスタイル
普段着をユニフォームにするという斬新な発想!
のちのロックスタイルに与えた影響はでかい!
中でも元々バスケットシューズだったコンバースのオールスター、特にハイカットの黒をロックスタイルの定番にしたのは間違いなくラモーンズだ
だがしかし、よくみてくれ、このジャケでは、誰もコンバースのオールスターなんか履いてはいない、どころか全員似ても似つかぬ靴を履いている、そう、ラモーンズは実はコンバースのオールスターなんて履いていなかったのだ!
それはこのジャケがファーストアルバムのものだから、とまず君は考えるだろう、たしかによくみると四人が着てる革ジャンもこれまたラモーンズの象徴でありのちのロックの定番アイテムとなるダブルのライダースではない、それぞれが黒くて皮というだけで現在のロックアイテムとは違うものを着ている、てんでバラバラだ。この頃はそんなに定まっていなかったってのもあるにはあるのだろう。
が、しかしダブルのライダースはのちにラモーンズ全員がお揃いで着だすが、コンバースのオールスターは実はその後もあんまし履いていなかったくさい。少なくともおらいが眺めた写真や映像の中ではほとんど履いていない。同じコンバースでもテニスシューズであるジャックパーセルの率の方が高い。では、なぜラモーンズ、もといロックンロールはコンバースのオールスター!ってイメージがついたのかと追求すれば、なんのことはない、ただの企業戦略、80年代くらいにコンバースオールスターの宣伝にラモーンズを使った?かなんかでそのイメージが広まって現在に至るって話でしかないらしい。世の中そんなもんだ。いつだってイメージは事実とは異なる。
まあラモーンズが広めたってことに変わりはないがね。
ついでだからメンバーの紹介もするかい?
一人一人紹介するほどぶっちゃけおらいラモーンズ詳しくないけどな
でも好きだよラモーンズ
大好きではないけど
みんなそうでしょ
あまりにも基本すぎる
基準すぎる
ラモーンズ好きじゃなかったらそいつパンクロックもロックンロールも好きじゃないでしょってレベルまでいく
あまりにも無駄がないのでもう人生に食い込むかどうかは好みのレベル、その人に恋するかどうかでしかないってレベル
まあだからメンバー紹介をするのは至極必然だな
ちなみにおらいはラモーンズのメンバーには誰にも恋してない
だから大切なバンドではない
当然のごとく好きってだけ
じゃあ普通に端からえーと、どっちの端にしようかな
うーんと、好きな方からにしよう
右端!
ディーディーラモーン!
そう、ラモーンだ
ラモーンズは全員ラモーンって苗字なのだ
勿論本名ではない
ラモーンって最初に名乗り出したのはこのディーディーラモーンじゃなかったかなたしか
ポールマッカートニーのいつだかのあだ名がラモーンでそれを真似たとかなんとかどっかに書いていたよーないなかったよーな
まあウキペディアでもみてくれ
あ、勿論パートはポールマッカートニーと同じベースだ
でもポールみたいに派手やかなベースプレイはしない
ほとんど一番上の弦を叩きつけるように連打だ
つーかラモーンズは全員そんな感じだ
でもステージ上の動きは派手だ
暴れまわるかのようなアクションでけっこーコミカルだ
おらいの好み的にはこのディーディーラモーンが一番好きかな
一番ひょうきんだからだ
おらいはひょうきんな人が好きなんだ
ザフーでいうとこのキースムーン的なポジションといえなくもないからなディーディーは
一番ぶっとんでる
どれくらいぶっ飛んでいるかというと80年代にソロでヒップホップのアルバムを出したほどぶっ飛んでいる
流行にはかなり敏感でかっこいいと思ったらなんでも御構いなしといった性格だったらしい
だからラモーンズではみんなにけっこー合わせているんだな
意外に律儀な奴だ
でもこのファーストアルバムのジャケとかではちゃんと50回転ズみたいなおかっぱ頭でいるけど途中からどうでもよくなったらしくて他のパンクスと同じ短髪のツンツン頭になったあげくけっこう後になってからこのタイミングで?ってみんな混乱するくらい突然脱退を表明していなくなってしまったほどの不良ではあるらしい
でも曲作りの中心はこの男だったというから面白い
ラモーンズは全員曲を作っていたけど一番多く作ってるってか有名な曲はディーディー率が高いらしい
俺あんま詳しくないからどれがどれってはいえないんだけどそうらしいということは知っている
で次は右から二番目、ジョーイラモーン!
ボーカル
ピンボーカル
マイクスタンド斜めに構えて突っ立って歌ってる
サイドのギターとベースはじゃんじゃん動くけどジョーイラモーンはそれに比べるとあんまし動かない
つーかでかい
でかいからあんまし動けないんじゃないかとも思う
マジ二メートルあるくさいからね
象とかと同じででかいやつは基本スローってのがこの世界の常識だ
だがNBAのバスケットボール選手はみんな二メートルあるけど動きは超速い
人間の場合には当てはまらないということか
だからジョーイラモーンがなんかスローなのはこいつの特性だな
なんかいつもサングラスかけてて眼球の動きが読めないから余計スローにみえる
いや実際は割とステージアクションしてるんだけどどうも様にならない
横の二人が機敏だということを差し引いてもなんというか、ちがう、かっこよくない、どうもなんというか、キュートだ
そう、ジョーイラモーンはキュートだ
ロックバンドのボーカルはコミカルであったとしてもクールな存在でなくてはならないのだが、ジョーイはなんかキュートだ
音楽の趣味もビーチボーイズとかフィルスペクタープロデュースのガールズグループとかそういうアメリカンゴールデンポップスが大好きだったらしいし
だからかパンクロックのイメージとしてがなりたててうるさいみたいなボーカルスタイルじゃないんだよな
なんか優しい含みのあるような歌い方だ
のっぽの人がちゃんとまっすぐ一生懸命歌っているという感じがする
パンクロックは速い!激しい!わかりやすい!だ
このわかりやすさの部分、ポップさと言い換えてもいいかもしれない
この部分を支えたのがジョーイのボーカルだと思って間違いないくさい
ラモーンズの演奏は激しいがジョーイは激しくない
ジョーイはポップだ
見た目は一番異様だがね
そしてジョーイも曲作りの中心だ
ジョーイの曲が一番わかりやすくてポップだという説もあるがラモーンズの曲は全部大体同じなのでそれは微々たる差のはずだ
そしてその右隣りはトニーラモーンだ
メンバーがいないからということでドラムをやらされた素人ドラマーだ
でもラモーンズのレコーディングプロデューサーでもあったらしい
けっこー初期にすぐぬけるんじゃなかったかな
ラモーンズはドラムはけっこー変わる
そこは他のバンドと同じだ
ドラムは大変な割にステージポジションが一番後ろでスポットライトが当たりづらいからやってらんねえってなる人が多いとかなんとかが理由かどうかはしらない
まあこのトニーラモーンはこのファーストアルバムで一人だけヘソ出しルックでなんかダサいから一番好きじゃない
しかもよくみると背伸びしてるし
特別小さいわけでもなさそうだがなにしろラモーンズは全員でかいからな
だからといって背伸びしているのはダサい
しかも背伸びしているのに横二人より背が小さくてもうなにがなんやらわけがわからない
ダサい
トニーラモーンが一番かっこよくない
サングラスもあんまし似合ってないし前髪の感じも気に入らない
でもあの単純だけどすごい頑張らなきゃいけないドラムスタイルを築き上げたのはこの男なわけだからリスペクトしておこう
次は最後!ジョニーラモーン!
ギター担当!
多分リーダー
もうこの男だけは最初から完全にラモーンズだ
最後までなに一つ変わらずラモーンズだったらしい
こいつがラモーンズだったといっても過言じゃないくらいラモーンズだったらしい
そもそもこいつが服装とか音楽スタイルとか全部仕切ってたらしい
おかげでラモーンズといえばこれ!っていうわかりやすさが生まれて後世の俺らは助かっている
ラモーンズは裏切らないからな
ラモーンズみたいな音楽が聴きたいと思ったらラモーンズを聴けばいいという当たり前のようで意外と当たり前ではないことが生まれた
みんな色々やりたがるもんだからな
まあそういう意味ではわかっているやつだったんだろう
悪くいうと窮屈なクソ真面目だ
だからあんまし好かれてはなかったらしい
でもそのギタースタイルの確立の功績はでかいとされている
ずーっとダウンピッキング
どんなに速い曲でも全部ダウンピッキング
叩きつける
連打する
エレキギターのリズム楽器としての特性を最大限に発揮
はっきりいって手首が大変だ
だがロックンロールは手首だ
昔のザフーのピートタウンゼントにあって現在のピートタウンゼントにないもの、それは手首感だ
現在のザフーの映像をみるとキースムーンとジョンエントウィッスルの不在と同じくらいピートタウンゼントの手首の不在を感じる
年には勝てないか、と
ラモーンズがいまも続いていたらジョニーラモーンの手首はどうなっていたのだろうか
なんだかこの男はジジイになっても手首使っているような気がする
それくらいこの男の手首には説得力がある
ラモーンズの演奏は簡単だ、はっきりいって誰にでもできる、だが楽じゃない、物凄く頑張らなきゃいけないというところがかっこいい
説得力がある
その源はこの男だ
間違いない
そしてギターソロは頑なにひかない
かっこいいぜ!
つーことでメンバー紹介は終わった
今日はケータイで書いているからそろそろ書き疲れてきた
つまりクライマックスは近い
パンクロックだから短く書かねばいけないからちょうどよかった
いつもみたくダラダラ長い文章は絶対にパンクロックではない
はやく激しくわかりやすくいくぜ!
つーことでようやく本日のお題であるラモーンズのファーストアルバム「ラモーンズの激情」の紹介にうつる
なんだこっからまた長いのか、なんて心配はご無用
ラモーンズのファーストアルバムは語ることなんかない
さっきも申した通りジャケ写が全てだ
ゴミのような男が四人でゴミのようなポップミュージックをはやく激しくわかりやすくやっているだけだからだ
これが全てだ
パンクロックそのものだ
つーかラモーンズがパンクロックだ
パンクロックとはラモーンズの音楽スタイルを指す言語だ
ロックンロールミュージックとはどういったものでしょうか?という質問にチャックベリーがやっているあれですって答えるのと同じようにパンクロックに関する同じ質問にはラモーンズのやっているあれですって答える
それが正解だ
そもそもパンクロックムーブメントって70年代半ばのニューヨークのCBGBってカントリーかなんかのバーにテレビジョンってバンドが出はじめたらメインストリームから相手にされない行き場のないゴミのようなバンド達が集まるようになっていってそこで個性を競い合い出したことから始まるらしいからニューヨークパンクって現代人が思い浮かべる所謂なパンクロックサウンドじゃないんだよね
おらいも最初聴いた時パティスミスとかブロンディとかこれのどこがパンクロックなわけ?ってなったもんね
現代人が思い描くパンクロックのスタイルを作ったのは間違いなくラモーンズ
それをロンドンのクラッシュとかが真似て流行らせたって流れみたい
つーことでラモーンズはパンクロックそのものだから語ることはそんなにはない
すぐ終わるから安心して読んでくれ
まずは一曲目!
The Ramones – Blitzkrieg Bop (Live)
邦題は電撃バップ!
絶対電撃バップの方がいい!
ブリッツクリーグバップって超言いづらいじゃん
まるで早口言葉みたいだ
電撃バップって名付けた奴は偉い
褒めてやろう
まず言っておくと、この曲が全てだ
この曲が好きじゃない奴はこのアルバムをきく必要がないしもっというとラモーンズ自体聴かなくていいというか極端にいうとパンクロック聴かなくていい
それくらい決定的なナンバーだ
ラモーンズってのは大体あとこれがずっと20年くらい続くって感じのバンドだ
大体全部おんなじ
このだからこのアルバムは多分全体で三十分もないと思うんだけどすげえ長く感じる
ずっと大体おんなじだから
つまり永遠を感じる
ロックンロールに永遠を感じるのはその無駄を削ぎ落とした単純さに美しさを感じるからだとテキトーなことを言っておく
単純で簡単だけど楽をしてないってところが特に気に入っている
この電撃バップは多分楽器始めたてのロック好きの奴らがバンド組んだら一番最初にやってみる曲ナンバーワンだと思う
おらいもボヘミアンズと別に遊びバンドやりたいと思って一度だけ高校の友人とヘッドホンズというバンドを組んでスタジオに入ったことがあるがその時やったのもやはり電撃バップだったな
おらいはドラム担当だったんだけど速いエイトビートってほんと大変なんだよね。全然うまく叩けないっていうか素人だから力み過ぎてちょー疲れる
簡単で誰でもできるけどけっこー大変でうまくやるのはそれなりに難しいという
ラモーンズの発明だこれは
誰にでもできるという概念をロックンロールに持ち込んだんだ
それまでは誰にでもできるものじゃなかった
少なくとも一生懸命楽器の練習をしなくてはならなかった
ラモーンズは素人でも一応はできるかっこいい音楽スタイルを作った
世界にこんなにバンドが溢れたのはラモーンズのせいだ
おかげでその分ゴミみたいなバンドも増えたがな
まあパンクロックは元々ゴミみたいなロックって意味だろうから間違ってないけどな!
やったぜベイベー!
つーことで終わります
え?もっと?
えーと
二曲目は
ビートオンザブラット
邦題はチビに一発
最高
完
ふっふっふ
どうだ
宣言通りはやく終わっただろう
パンクロックだからな
当然だ
つーことでここからはしばらくパンクロックのファーストアルバムの紹介が続くのかな
うーん、わからん
でも次回は確実にそう
「パンクロック誕生!ロックンロールは気合いだ!」
「パンクロック登場!ロックンロールは気合いだ!」
と続いて次回からテーマを
「パンクロック流行!ロックンロールは気合いだ!」
と題してついにあのセックス・ピストルズのファーストアルバムの話をしようじゃないか
やったね!
つーことでじゃあな
またな
バイバイな
Ramones – Beat On The Brat Live San Bernardino