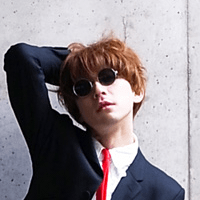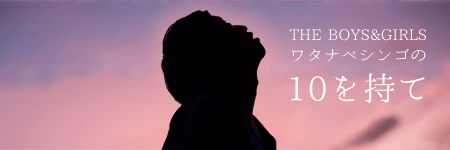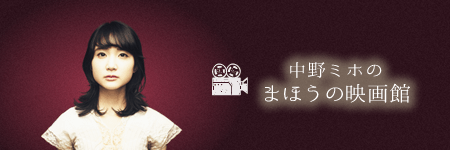平田ぱんだのロックンロールの話
第46回:アークティック・モンキーズ『Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not』
どーも、イェイイェイ平田です。なんでもイェーイって言っとけば丸く収まると思ってるタイプの基地外です。だ、誰が基地外だ! まともだ、まともなはずだ、その証拠に穏やかだ、日々を噛み締めながら。つーことで唐突に今回紹介するロックンロール・ファーストアルバムは、こいつだ!
アークティック・モンキーズの『Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not』だ!!!
史上最強のロックンロール・ファーストアルバムと言い切っても過言じゃあない。少なくとも指折り候補の中には余裕でエントリー、歴史的意義という点においてはストロークスのファーストアルバムに座を譲る事になるだろうが、完成度という点においては00年代ナンバーワン・ロックンロール・ファーストアルバムと言い切って間違いないだろう。
A面1曲目!「The View from the Afternoon」!
ヘヴィなイントロからの多彩なビートとめくるめく展開で畳み掛けるアクモン・ワールド全開楽曲でしかない、これがアークティック・モンキーズだ!どうだ! まいったか! とにかく、とにかくビートがいい! とにもかくにもアークティック・モンキーズ、日本略名で書き表すとこのアクモンは、ビート感覚にガチクソ優れている、はっきりいって才能がある! プラスそこに意識的であることがわかる、才能プラス学があるって話。ロックンロールはビート・ミュージックだ。アークティック・モンキーズこと日本略名で書き表す所のアクモンにはビート感覚しかない! しかも前のめりでいて溜めのきいた、そう、ロックンロールのスピードとビートがある! それは若者のものだ! 四人の若者が結託して世界の片隅を中心地に変えんとするあのビート感がアクモンにはある!
まずその爆心地メンバーを紹介しよう、まずはドラマーのマット・ヘルダースだ! こいつはうまい! とにかくうまい! うまいっていうか才能がある! 才能がゴイスー! まるでドラムを叩くために生まれてきたような男だ!ドラムを始めたきっかけは「バンドにドラムしかポジションが空いてなかったから」だそうだが、これぞ神の思し召しだ! こいつはすごい! 正に才能がゴイスーだ!
バンドを始める前から現代っ子らしくヒップホップが大好きヘッズだったらしいが、そんなリスナー時代から培ったビートの重要性に対する意識の高みがあの00年代最高のリズミカル・テクニカル・ドラムに繋がっているらしい。マット・ヘルダース! こいつは間違いなくキース・ムーンやジョン・ボーナムやレニなどといったドラムがメロディアスにフレーズを奏でてしまうことができる、いわゆる「歌う英国ドラマー」の系譜に連なる重要人物だ! 00年代最強のドラマーの称号はこいつにしか与える気が起きない! 最高! アークティック・モンキーズのファーストアルバムはこいつなしでは語れない! 成り立たない! イエーイ、のりのりだっゼーい! この曲を脳内再生する時、僕らはいつだってドラムのフレーズから鳴らす。トイレで出にくいうんこをしてる時には決まってこの曲のドラムを脳内再生してるっていうか、手も動かしてる! もうこの曲を脳内で再生させなかったら、うんこ出ないかもしんまい!ってぐらいにマスト! うんこバシっと出したい君に断固オススメ! それがこの曲だ! いいな!
そんな感じでこの曲を聴けばわかる通りアクモンはビート集団なんだ。全員ビート、全楽器ビート、全ての楽器を打楽器として使用している。しかも言語までもビート、歌までも打楽器として使用している。こんなロックンロールバンドは今までどこにもいなかった! とにもかくにもビート、ビート、ビートまみれ。しかも若いビート。前のめりで向かっていこうとする意思のある意識的なビート。ロックンロールはビートだ。僕たちはずっとこんなバンドを待っていたんだ!
A面2曲目!「Bet You Look Good on the Dancefloor」!
バンドの代表曲その1。これぞアクモン。年寄りには絶対にこの若者のグルーヴは出せない。この曲のミュージックビデオがCD音源じゃなくてバンドの生演奏を一発ドリした映像なんだけど、あれ、考えたやつ、誰? あのミュージックビデオ、死ぬほど正しいと思う。これ以上なく若者であることを示す姿を記し、記録した非常に正しい映像。これぞ若者のすべて! アークティック・モンキーズのファーストアルバムの感動の源はこの「若者であること」にあるよな。おっさんがやるもんじゃねえんだよ、本来、ロックンロールなんてもんはよ。このご時世じゃおっさんのやるロックンロールにも意義は沢山見つけられるし、おっさんがやるからこその生き様の重みによる感動も次々に生まれているし、そもそもおっさんしかロックなんかやってねえって話もあるにはある。でもやっぱ本来は若者のものなんだよ、ロックンロールは。若者の前のめりな衝動で中途半端な年取っただけキャリアがあるだけのおっさん連中なんかガンガンどかしてくべきなんだよ。マジ、若者ロックやれよ。でも、もうロックなんか日本以外じゃ見向きもされてないって噂を聞いたことがある。エレキギターの音が鳴った瞬間、もう「おっさん音楽だ」って飛ばされるんだってさ。んなアホな! ごく一部の国のごく一部の若者の話だといってくれー! だってロックンロールが一番かっこいいだろが! ほらほらほら、ホラー!
このアクモンのファーストアルバムが発売されたのは、えーと、2006年か。13年も前の話になるのか。マジでこれ最後の大ヒット・ロックンロール・ファーストアルバムだよね。ファーストって単語を抜いてもラストかもしんまい。その後、もちろんいくつかいいロックバンドはいたんだけど、ワールドワイドって話だとマジでこのファーストアルバムが最後のビッグ・センセーションくさいな。寂しー。セックス・ピストルズのファーストが77年でオアシスのファーストが94年だから、そう考えると、いうほど空いてないな! まだまだダイジョーブ、ダイジョーブ!
そんな今んとこ、最後の大物状態のアークティック・モンキーズですが、このバンドが歴史上の他の大物バンドたちと違うことといったら、間違いなく「インターネット登場以降のバンド」ってことですよね。この曲なんかデビュー曲なのに初登場1位を記録したらしいですからね。ロックンロールバンドのデビューシングル曲が初登場1位になったケースはイギリスじゃ初らしいっすよ。そらそうだ。だって普通はデビューしてからだんだんと名が売れるんだからさ、アイドルとかなら別だけど。でもなぜアクモンはデビューシングルが初登場1位なんていう、オアシスもビートルズも成し得なかった偉業を達成することができたかといったら、理由はただひとつ!「インターネット上でもうとっくに人気者だったから!」だそうです。元々はバンドがライブ会場で無料で配ってたデモ音源をファンか誰かがネット上でばら撒いて、「シェフィールドに最高のバンドがいる!」なんつってイギリス中で広まったらしい。今じゃそんなの珍しくない話だけど、当時はそんな事例がなかったから、みんなそれに対してケッコー懐疑的だったのは覚えてるね。だってそれまではメディア主導が当たり前だったもん。流行は雑誌テレビとかのメディアが作ってた。だから騙されたなんて思ったことなら何度もあるよ。
個人的な話をすると、アクモン全員、僕より年下だったからさ、生まれて初めての年下のロックスターになりそうなやつらに夢中になるまでケッコー時間かかったね。だって憧れてなんぼじゃん、ロックスターなんて。今じゃ一切そんな感情ないけど、若者の時分には年下に憧れるなんてありえないじゃん。「オアシスのアルバムが最速売り上げ記録を超えた!」なんて聞いた時、若干なんか悔しかったもん。俺のオアシスよりも上になるなんて! 若僧! 許せねえ! みたいになったもん。しかもオアシスみたいに「無敵のメロディ!」って感じじゃないじゃん? アクモンはもっとバンド力とリリックスの機知で勝負してくるタイプだったから、僕みたいな当時の日本のロック好き若者にはかなり受け入れづらかったかな。つーか周りが全員そうだった。「アクモンのファースト最高」ってリアルで言ってるのは、うちのバンドのベースの人が初めて、みたいなレベルだったもん。少なくとも僕の周りではそうだったかな。でも今ではー! アークティック・モンキーズがー! とっても大好きでーーーい!!! 最高のバンド。一家に一台。必ずレベル。
Arctic Monkeys - I Bet You Look Good On The Dancefloor (Live at The Apollo)A面3曲目!「Fake Tales of San Francisco」!
和訳だと「サンフランシスコのインチキ物語」だそうです。基本的にアクモンの歌詞はリアルから得た妄想個人感情物語だよな。だから曲の展開もなんか複雑っつーか単純に多いんだよな。すべてはギター・ボーカルであるアレックス・ターナーのせいだよな。プロフィールには「バンドの作詞家」って、よく書かれていたよな。ソングライターじゃなくてね。それくらいリリックに重きがおかれてるんだな、アクモンは。詞先な場合が多数らしいからな。詩に合うビートが見つからないからお蔵入りになってた曲を、今回のアルバムでようやく入れた、みたいな話もどっかで言ってんのを見たから、マジらしい。それはアークティック・モンキーズのキッズ時代のメイン・リスニング・ミュージックがヒップホップだったからってことが要因のほとんどらしい。ロックンロールに出会うまではむしろ「ヒップホップこそが俺たちの世代の代表音楽!」って思ってたりもしていたらしい。でも実はジャムやスミスやオアシスみたいな古めかしいのもこっそり好きだったらしい。でもロックなんておっさん音楽だから大っぴらに好きだなんて言えねえよって思ってたとこに登場したのが、かのザ・ストロークス! ストロークスの登場によって一気にロックンロールにシャレオツが取り戻された! その効果によってアクモンのみんなさんは「ロックンロール最高!」ってなって自らのバンド結成!って流れらしいです。いやー、ストロークスがいてくれて本当によかった。おかげでアークティック・モンキーズが登場したぜ! やったね!
A面4曲目!「Dancing Shoes」!
ダンサブルじゃないか。そうさアクモンはダンサブルさ! だってダンサブル世代なんだからね! いわゆるダンスミュージックの影響なんて、そこら中に受けまくりなのさ! 大雑把にいうとこの当時のダンスミュージックってのは黒人の複雑なグルーヴビートを簡略化したディスコ音楽から派生した「四つ打ち」ってやつを基調としているやつのことを指すことが多いだ。ディスコミュージックの誕生によって、音楽は死んだと言っている人が、この世には最低30人くらいはいたくらいだけど、もうすっかりこの世界のメインミュージック界を席捲しちまったと言われてなくもない。だがロックンロールはなんでもありの雑食ミュージック、節操なしで飲み込み突き進む、センスのみを頼りに!ってな感じでアークティック・モンキーズはロックンロールだから、ダンスだろうがなんだろうが関係ない。ロックンロールの前ではすべてロックンロールに変えられてしまう。ロックンロールには敵わない! といった按配なのだ。
そういえばアークティック・モンキーズが出てくる寸前まですげえ嫌だったわ、イギリスの流行り音楽。04年くらいでガレージ・ロックンロール・リバイバルが完全に収束。ポストパンク・リバイバルとかディスコパンクとかっつってイギリスから四つ打ち系のロックバンドばっか売り出されてた。多分04年にフランツ・フェルディナンドが四つ打ちポップ・ダンス・ロックで世界的に売れちゃったのがいけないんだと思う。フランツ自体は嫌いじゃないというかむしろ好きなくらいだけど、チャラいから嫌だったな、当時は。やっと世界的に売れたイギリスのロックバンドがこれなの? みたいな感じは確かにあった。当時はせっかくの世界的なロックンロール・ブームなのに肝心のイギリスからビッグ・ロックバンドが一向に登場しない状態だったからね。え?コールド・プレイがいたじゃないかって? 君にはあれがロックンロールに聴こえるの? 変わってるね、君。
そんなこんなで四つ打ちだろうがヒップホップだろうがなんだろうが、すべて飲み込んで混ぜ込んでストレートに突進してきたアークティック・モンキーズの登場はハッピー以外の何ものでもなかったはずだね。最初は素直になれなかったけど、一度受け入れてしまったら、一気に心の極上の域に行ったぜ。兎にも角にもまず若い! やっぱ若者じゃなくっちゃな、時代のロードの方向を変えるロールバンドはよ。フランツみてえな90年代から音楽活動をしてるような、アラサーのロートルにイギリスの時代代表ロックは任せられるわけがねえ! 若者の代弁者足り得るわけがないんだ、アラサーのおっさんには。ロックンロールは若者のものだよ。30越えに時代は決して味方しない。するべきじゃない。少子化反対! 産めよ増やせよの大号令! そして全子供、エイトビートで頭をおかしくしちまおうぜ! オッポオッポ。
A面5曲目!「You Probably Couldn’t See for the Lights But You Were Staring Straight at Me」!
馬鹿野郎! まだ5曲目なのか! かなり省略した早いペースで書いてるはずなのにまだ半分もいってないのか! 許せねえ! この曲のタイトルの長さも許せねえ。英語喋れない人間からすると一切覚える気が起きない。きっと僕は一生この曲のタイトルを覚えることはないだろう。僕はこの曲をずっと死ぬまで「アクモンのファーストの5曲目」と呼ぶはずだ。ようやくのエイトビート系ストレートナンバーがきたと思ったら、この有様。ふざけやがって。大体にしてこのファーストアルバムのタイトル自体が長いじゃないか。ふざけやがって。記憶をどうにか辿ってどうにかどうにか文字打ちできるかどうかってくらいこのアルバムのタイトルは長い。僕は一生死ぬまでこのアルバムのタイトルをフルで口ずさむことはないだろうな。ちなみになんかイギリスの「土曜の朝はなんちゃらかんちゃら」みたいなタイトルの映画の中に出てくるセリフなんだそうです、このアルバムのタイトルは。だからそれに準じて土曜の夜から日曜の朝までのストーリー的な流れを重視した曲順らしいよ。コンセプトアルバムってわけじゃないけど、そういう流れを意識してんだってさ。後付けでしかないんだろうけど、歌詞に重きをおいたタイプのロックバンドらしい行いですよね。
ちなみこのアルバムのジャケのおっさんはバンドの友人だそうです。喫煙を推奨してる!とかって批判を浴びたこともあるそうです。それにしてもバンドの友人にしては老けてるな。このアルバムを出した時アクモンは20くらいのはずだけど。そういう意味ではこの当時のベースのアンディ・ニコルソンも年の割には老けてるよな。太ってるからかな? でもこういう諍いの際に頼りになりそうな喧嘩の強そうな見た目をしてるやつはバンドにひとりは欲しいよね、ほんとは。デブは喧嘩が強いは定説だ。でもそういう奴に限ってメンタルが弱かったりして、このファーストアルバムの時のベースは過酷なツアースケジュールに耐えきれず、アメリカツアーに行くことを拒否して、バンドをやめることになるそうですけども。こいつのベース、好きだけどな。見た目に似合わず滑らかにうねってきて。やっぱバンドにひとりは太っちょが必要だよなー。なんて思ったり思わなかったり。次!
A面6曲目!「Still Take You Home」!
ようやくアナログだとA面ラストのナンバーに到達だ。せめてくるぞー! よーするルースターズの「恋をしようよ」だな。こういう歌をうたう時こそ、ロックンロールバンドは前のめるもんだ。必然必然。ここでA面終了!
B面1曲目!「Riot Van」!
A面をあれだけバシバシ勢い責めしてきておいて、いきなりのこの落ち着きっぷり! 大人の魅力すら感じさせるほどのこの歌唱っぷり! ま、ま、ま、ま、まいりましたー!ってな具合。いやー結局のところ声がいいよね、アクモン。ギターボーカルのアレックス・ターナーの声がいい。だから成り立つ。結局は声の良し悪しなんですよ、ロックバンドなんてもんは。加えて顔もいいときたもんだ。ロックバンドという立場において、これは時に足かせになることもある要素だ。事実、デビュー当時はアレックスのその可愛い系イケメン顔のせいで、アイドルバンドのファンみたいな若い女の子たちまでライブに押しかけるなんて状況もあったらしい。アクモンみたいなタイプのバンドからしたら、多分嫌だったと思う。あくまでも想像だとだけど。でもよ、ロックバンドなんて女の子にキャーキャー言われてなんぼだろ?って思うよ、僕は。顔なんかかっこいい方がいいに決まってんじゃん。
なんか一時開き直ったかのごとく「俺が現代ロックを背負っちゃる!」みたいな感じで、急にリーゼントにしてステージで堂々とスター系パフォーマンスしてたよね、アレックス。15年くらいだっけ、あれ? あれ好きだったんだけどなー。なんかこないだのアルバムの時にはロン毛のヒゲのピアノマンみたくなっちゃってて、残念っちゃ残念だった。つーか、こないだのアルバムすごくよかったけど、残念だったよね、色々。内容はすごくよかったんだけど、全然ロックンロールじゃないんだもんよ。もう次のアルバムを心待ちにするイギリス・ロックバンドなんてアクモンだけなんだよ、僕は。ロックンロールやってくれよー。不毛なんだよー、マジであまりにもー。ロックンロールやらないんならアルバム出さないでってくらいだよ、ほんと。でもこないだのアルバム自体はすごくよかったよ! ピース。
B面2曲目!「Red Light Indicates Doors are Secured」!
このアルバムで最もループ系ミュージックしてるやつ。当然そうなると必然的にラップの要素が際立つ。ラップってのはひと言でいうと「リズムにのって韻踏むこと」のはず。メロディはそこまで重視せず、フロウとかいってビートにどう乗っかって、どう言い回すかってとこに重点が置かれてたりする。シンプルなものだからこそ、重要になるのが韻を踏むこと。日本人にはこの素養がないことが、日本でヒップホップ・ミュージックがくすぶってる理由らしい。日本語の構造的に綺麗に脚韻を踏むためには、倒置法とかつって不自然なやり方をやんなきゃいけないからね。普段のしゃべり言葉と違うものにせざるを得ない。英語圏のみならず、漢文とかも、日本でいうと、この倒置法が普通の状態。「韻を踏む」行為自体が、ダジャレとしてしか機能発達してこなかった日本ではこういう曲はなかなか成立しないし、作るためには結構な努力が必要なはず。歌詞に限らず普通の詩でも韻を踏むなんて当たり前に行われてきたどころか必要不可欠くらいらしいからね、海外では。いいなー、ラップ。だってかっこいいもん。日本人は大人しくメロディ重視で頑張りゃいいっていう人もいるけど、やっぱラップはかっこいいよ。
アークティック・モンキーズの何がかっこいいって全てがリズム楽器として機能してることだもんな。ドラムとベースだけじゃなく、ギターもそしてボーカルまでも全てリズム楽器、打楽器として機能している。ボーカルをリズム楽器として機能させるのは、日本語じゃかなりの苦難。僕もこの初期アクモンのロックとラップの中間みたいながやりたくて、自分バンドの持ち曲でたまーにちょいちょい挑戦はしてんだけど、なーんかうまくいかないんだよなあ。英語はっきり言って羨ましい。でも英語を喋れないくせに英語で歌ってる日本人は違うと思ってる。英語で歌うナンバーもあるとかならわかるけど、持ち歌が全部英語は流石に理解しかねるわ。
B面3曲目!「Mardy Bum」!
初期のアクモンつったらマイナーで前のめって突っ込んでくるかっこいいロックンロールって感じだけど、こういう曲があるから信用できる。これがなかったら好きになってないかもしんまいくらいに。B面1曲目の「Riot Van」もそうだけど、そこらへんがアレックスの趣味趣向によるもんなんでしょうな、きっと。バンドでじゃなくアレックスが単独で作ったと思われる曲がとっても好きなんだよな、僕。でもそれでいっぱいになった4枚目はあんまし好きじゃなかったりする。やっぱアルバムに1曲か2曲入ってるくらいがちょうどいいんだよな、アレックス単独曲は。5枚目にしてファースト以来の傑作アルバムとなる『AM』収録の「No.1 Party Anthem」なんか死ぬほど好きだもん、僕。つーかよ、極論いうとよ、やっぱ女の子のことを歌ってなんぼなんよ、ロックンロール・ソングなんてもんは。生きるか死ぬかの次に大事なものって女の子じゃん。「大好きなあの子の心を僕だけのものにするために、どうすべきか? と考える迷いながらの衝動」なんだよ、重要なのはいつだって。恋とロックンロールは同じだよ、向いてる方向と勢いが完全に。
B面4曲目「Perhaps Vampires is a Bit Strong But…」!
オラオラオラー! オラオラオラー! オラオラオラオラオラーーー!!! このアルバムで最もヘヴィなサウンドのナンバーだ。アクモンに終始流れるこのヘヴィロック的ニュアンスは全てギターのジェイミー・クックの趣味らしい。アクモンっつったら根幹はボーカル・ギターのアレックス・ターナーとコーラスドラムのマット・ヘルダーだろって思われがちだが、意外と目立たない地味な立ち姿だが、こいつの趣味趣向意向が結構バンドを動かしてたりしているらしい。そもそもこの男とアレックス・ターナーが始めたバンドだし。バンド名もこの男が名付けているらしい。目立たないだけでかなり発言権を持ってるらしいっていうか。そもそもアクモンって全然ワンマンバンドじゃないらしい。ボーカルのアレックスが実権を握ることが多々あるだけで、基本民主主義というかアレックスがスランプで煮詰まってる時とかは、ほっといてバンドだけでどんどん制作をすすめるとか普通にする、とどっかで書いてるのを見た気がする。レディオヘッドとかもそういう感じらしいけど、そういう裏の制作部分はリスナーには一生わからん話ですよね。ということで今日こそ短く書くつもりだから次! もう大分長くなった気もするが。
B面5曲目!「When the Sun Goes Down」!
はいきた、一番好きなやつ。代表曲のひとつ。もう現在じゃライブでやってないけどA面2曲目のアイベットなんたらに並ぶ初期の代表曲のひとつ。オールド・メロディなコード進行からの冒頭ムードから打って変わっての、あの全開の展開は何度聴いても燃える。なんか当時のアクモンの練習スタジオが風俗街の真っ只中にあったらしく、その情景を妄想物語調にして歌い展開したナンバーらしい。ポリスの売春婦に恋をした少年の歌だかなんだかの「ロクサーヌ」とかいう歌を引用しているらしい。僕は英語がわかんないから、知らんけど、とにかくそういう感じらしい。とにかく物語に準じた曲構成になっている。アクモンのあのシンプルでヘンテコな曲構成は大体歌詞の物語に準じているがゆえらしい。
こういう路上の他者からみた情景みたいなを書くのがアレックスはうまくて、バンドで成功しなかったら、文学を学びに大学に行こうとしていたらしい。でもバンドがイギリスのロック史上でも指折りの成功を収めてしまったから、そうはしなかったらしい。学校の成績優秀で顔が可愛くて音楽の才能があってって、なんて恵まれている男だろうか! しかも両親が音楽好きというか、音楽の先生で小さい頃から自然とピアノを習ったりしていたとな。とんだラッキーガイじゃないか! こういうやつが「売春婦のあの子を遠くから見ていることしかできない俺……きっとあの男が全部悪いに違いない! なんて悪い奴だ!卑劣漢! 許せねえ!」みたいな歌を作るからたまらんのだよね。基本的にクールに情景のみを歌っているところが逆に気持ちの裏打ちを感じる! なんて話も。なんにしてもこのアルバムで1、2を争う傑作曲なことに変わりなし。いやっほーい。
B面6曲目「From the Ritz to the Rubble」!
そして夜も深まり、クラブに行ったらセキュリティーの人に未成年だからダメってはじかれて散々な気分で帰って、起きたらセックスした女の子が昨夜のイメージと全然違うじゃないかっていうか、昨夜のことぶっちゃけあんま覚えてないわ、なんか重要なことに気づいたつもりでいたはずなのに……! みたいな歌、だったはず。こういう日常のストリート系なリアルを歌うみたいなのもヒップホップゆずりでもあるみたい。このアルバムは、一応、土曜の夜から日曜の朝までの物語となっているらしいので、ここでようやく朝にたどり着いたってわけだ。
つーか、初期アクモンってストーリー性のある複雑な展開を持つ曲を沢山やるけど、どの曲にもちゃんとシンガロングポイントがあるのが偉いっつーか、イギリスだよね。サッカーの盛んな国だからなんかね? みんなで合唱したがるよね、イギリス人って。このアルバム収録の「Mardy Bum」とかシンガロングポイントないと見せかけて、ライブ映像で見ると、イントロのギターリフをみんなで合唱するという大好きっぷり。イギリスのフェスとかでロックライブ見たら楽しそうだなー。一回行って見たいわ、イギリスのロックフェス。
B面ラスト曲「A Certain Romance」!
バカヤロー! 終わりだ、終わりー! これで終わりだ、バカヤロー! いつまでもやってられっか、ロックンロールなんかよー! さっときてパッとやってばっと終わってヒョッヒョーだろがロックンロールなんてもんはよー! やってられっか、このクソが! どうせわかりっこねえ! わかってたまるか! 初めから知ってたんだよ、初めから俺はよぉぉぉぉ! と行った内容の完璧な締め。00年代初頭というロックンロール最後の夢であり、終着地点とも呼べる集大成楽曲。00年代初頭のロックンロール・ブームってのはよーするこういう曲のことだったんだ。あとは特にないよ。そしてこの完璧なロックンロール・ファーストアルバムの完成とともにロックンロールはメインストリームからまたはずれる。仕方ない。ブームの集大成とも呼べる時代の傑作ファーストアルバムが出てしまったんだから。またロックンロールの役割は終えた。次はいつだろう? もう来ないのか? 残念だ。あと2年待ってやる。それまでに来ないんだったら、もういらない。大人しく僕はおっさんになるよ。急激に老けてやる! ロックンロールの、バカヤロー!
みたいな。次回は、いよいよ佳境。我が国日本の、最後の重要ロックンロール・ファーストアルバムについて話すよ。つーことで唐突に、じゃあな。アディオース。
Arctic Monkeys - When The Sun Goes Down (Official Video)
平田ぱんだ『ロックンロールの話』単行本
2019年10月1日(火)発売
著者:平田ぱんだ
仕様:A5変形 全232ページ(特製ケース/特製しおり付き)
価格:2,400円+税
発行:株式会社CHINTAI
編集:Rock is/DONUT
ブックデザイン:山﨑将弘