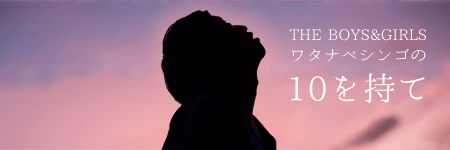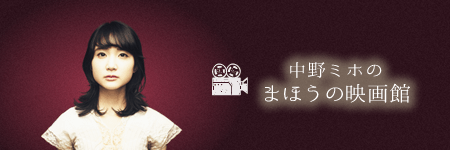編集部Like it
森内淳の2018年2月 ライブ日記
今回は2018年2月のライブ日記。2月は大量の原稿書きが忙しくて、なかなかライブに行く時間がつくれなかった。多忙さがたたって、ライブのメモとる心の余裕がなかった。今回もまた見たライブのなかから適当にチョイスして書き綴ったわけだが、印象に残ったライブというよりも、メモが残っているライブを中心にピックアップした。ライブ・レビューの体裁は整えてはあるが、あくまで日記として楽しんでいただければ嬉しいです。
2月8日(木)THE PREDETORS Zeppダイバーシティ東京
ザ・プレデターズを見にお台場へ。クアトロのライブを見に行けなかったので、今日が今ツアー初のプレデターズ。メンバーはthe pillowsの山中さわお、GLAYのJIRO、Scars Boroughの高橋宏貴。作品ごとにコンセプトを決めて音楽で遊ぶことをテーマにしたバンドだ。派手な照明とデカい出音、楽曲の方向性もピロウズとは違うので、山中さわおにとっては違う筋肉を使うライブになっていると思う。JIROにとっても、衣装や演出、会場の規模感も含めて、いつもとは勝手が違うはず。そんな先輩方を相手に奮闘する高橋宏貴。それぞれ勝手の違いを乗り越えてひとつのロックンロール・バンドになろうとする姿が初々しい。
2月9日(金)がらくたロボット Zher the ZOO YOYOGI
21歳のヤマモトダイジロウ(vo>)、20歳のムラカミフウタ(ba)、26歳のイノウエタカヒロ(dr)の神戸在住の3ピースバンド、がらくたロボット。今日が初見。70年代後期のパンクやロックンロールを洗練した解釈でタイトに鳴らしていて驚いた。まだ21歳とかだよね。ミッシェル・ガン エレファントっぽくもあるという評価もあるけれど、ドクター・フィールグッドのようなギターのカッティングをやるわけではなく、どちらかというと、ザ・クラッシュ、ザ・ジャムやザ・フーの匂いも感じる。これは後で聞いた話だが、本人はエコー・アンド・ザ・バニーメンの研究家らしい。本当に21歳なのかよ。最近、ライブハウスによく行くのだけど、日本のロック バンドは日本のロック バンドに影響を受けすぎている傾向にある。それはそれでいいんだけれども、そのミュージシャンが一体何を聴いてこうなったのかを掘っていけば、さらなるオリジナリティを生み出せるのになあ、と思う。ぼくがよく「J-POPの文脈」という言葉をテキストに使うのはそういうことだ。がらくたロボットが妙に耳にフィットするのは、触手が洋楽まで到達しているからだと思う。
2月10日(土)浅田信一 三軒茶屋GRAPEFRUIT-MOON
今日は浅田信一のライブ。90年代SMILEで活躍、現在はプロデューサーとしても活躍しているアーティストだ。ぼくがNHK-FMでミュージック・スクエアという番組を手伝っていた頃からのご縁だ。彼は、ザ・コレクターズの古市コータローのソロ作品もプロデュースしている。その浅田信一が新作「あいのうた e.p」をリリース。全国ツアーをやるということで初日にお邪魔した。今回はバンドではなくアコースティックソロライブ。いつもは代々木でやっていたのだが、浅田信一が20年暮らす「第2の故郷・三軒茶屋」へ。曰く「ぼくの家にみんなを招待したような感じにしたかった」。会場の雰囲気がポップで、浅田信一の雰囲気とすごくマッチしている。普段はカフェをやっている場所だそうで妙に居心地がよかった(この日はテーブルを全部取り払ってあった)。早くも「浅田信一のホーム」感が漂っている。会場に漂うリラックスムードがアコースティック・ライブというスタイルに妙にマッチしていて、最初から最後まで楽しめた。いつもはどうしてもバンドサウンドが欲しくなったりもしていたが、今日はそういう気持ちにはならなかった。一番よかったのが中盤の新曲コーナー。才能あるミュージシャンは新曲をつくり続けてなんぼだ。ニューアルバムが名盤になる予感がぷんぷんしていた。
2月11日(日) SCOOBIE DO ZeppTokyo
スクービードゥーは昨秋、13枚目のアルバム『CRACKLACK』をリリース。その全国ツアーのファイナル公演をZeppTokyoでおこなった。今回のライブは家族連れのエリアやとにかくがむしゃらに盛り上がれるエリア、ゆっくり座って見られるエリアなど、様々な席種が用意されていた。年代を超えて彼らのファンクとロックとダンス・ミュージックを楽しんでもらいたいという気持ちが伝わってくる。そういうところが評価できるし、多くの人に好かれる理由だと思う。会場に入るとステージから花道がのびていた。その先に(ローリング・ストーンズでいうこところの)Bステージがつくってあった。それだけでも通常のライブとは違う雰囲気を醸し出している。というわけで、ファンキーなスクービー、ロックンロールなスクービー、(今回のアルバムを象徴した)メロウなスクービーに加え、Bステージにおけるアコースティックなスクービーまで、実に濃密な2時間半のショウになった。
2月16日(金)エルモア・スコッティーズ他 Yokohama B.B.street
岩方ロクロー企画のイベントを見に横浜B.B.ストリートへ。岩方ロクローはニトロデイやエルモア・スコッティーズでドラムを叩いている19歳のミュージシャン。エルモアではすべての楽曲をつくって歌もうたっている。横浜方面では若いバンドたちの中心人物として知られている。会場に入るとニトロデイの小室ぺいがDJをやっていた。ニトロデイの残りのメンバー、ギターのやぎひろみとベースの松島早紀、それに岩方ロクローはbetcover!!のバックバンドをやるので、今日はニトロデイとエルモア総出というわけだ。トップバッターはエルモア・スコッティーズ。なんで主催者がトップバッターなのかよくわからないが、まぁそれも彼なりの気遣いなのだろう。10代が切り取った日常の風景とそれを突破していこうという意志が宿った歌は今日もライブハウスの空気を震わせた。彼らは現実を淡々と捉え、静かに前へ進んでいく。その冷静な視点がとても新鮮だ。真ん中にある考え方や価値観は同じでも、表現方法(アウトプット)が違うのだ。ぼくらが10代だった頃よりも、今の10代は大人だということだ。しかしサウンドはクラシック・ロックのツボを心得ている。次に登場したのがシンガーソングライターのリツキ。学校を出るのが遅くなり、走ってライブハウスまでやってきたそうだ。10代という言い方は一歩間違えば、プロモーション・ツールのひとつに成り下がることもあるが、こういうMCを聞くと、10代という言葉にやたらとリアルに響く。ロックンロール・キャン・ネヴァー・ダイなのだ。トリのbetcover!!はヤナセジロウのひとりバンド。ファンクやR&Bやアシッドジャズを基調としたグルーヴィなサウンドで、フェスのコンテストを勝ち抜いたこともある。あえてカテゴライズすれば、サチモスやナルバリッチの現代的シティ・ポップスの系統に入るのだろうが、ライブはもっと即興的な要素が入ってくる。すべてヤナセジロウが指揮者となり、演奏のタイミングなど、その場で指示を出すのだが、そのインプロビゼーション感が全盛期のチャック・ベリーのライブのようで面白かった。しかもバックメンバーが前述したように(小室ぺいを除いた)ニトロデイの3人だ。そこに生じるカテゴライズからはみ出したグルーブをも掴もうとしているように見えた。3組とも優秀なアーティストばかりだった。足腰が悪いので、イベントはお目当てのアーティストしか見ないことも多い。が、岩方ロクローの企画は別だ。次の自主企画は彼が20歳になる前日、4月22日(日)に同じB.B.ストリートで行われる。長丁場だけど見に行こうと思う。
2月18日(日)THE COLLECTORS SHIBUYA CLUB QUATTRO
ザ・コレクターズは、渋谷クアトロで月一回、年間を通してワンマンライブをやっている。これはほぼ毎年企画されていたクアトロ・マンスリー(3ヵ月〜5ヵ月連続でマンスリーライブをやる企画)の毎月バージョン。言わば「リアル・クアトロ・マンスリー」だ。先月も書いたと思うが、このシリーズの難しさは、めったにやらない曲を入れることと、毎月セットリストが違うこと。例えば、ツアーだったり夏フェスだったりすると、メニューはほぼ固定されるが、クアトロ・マンスリーは毎回1からセットリストを考え、それを練習して、披露しないといけない。ここ2年くらいで、コレクターズのリズム隊が変わってしまったので、このメンバーで初めてやる曲も少なくない。今日も1曲目から20年ぶりに演奏する「BOXING TIME」を投入。「愛してると言うより気にってる」や「ガリレオ・ガリレイ」「ベイビー・ハリケーン」「誰にも負けない愛の歌」などここ最近のライブではセットリストからはずされていた楽曲も次々に登場。今日も「この日限定のメニューのライブ」になった。日本武道館公演以降、平熱に戻るかと思いきや、ますます音楽に対する熱量は上がる一方だ。ちなみに6月までのチケットは一般発売時に即完。
2月23日(金)THE BOHEMIANS 下北沢GARDEN
下北沢ガーデンへボヘミアンズのワンマンライブを見に行った。年末から今月まででボヘミアンズのライブを3回くらい見ている。彼らとは単行本『ロックンロールが降ってきた日』からのお付き合い。初めてライブを見たのは現・夏の魔物の成田大致のイベントだった。毎度書くけど、洋楽の艶やかさとチャーミングさを取り入れたバンドがこの時代にいるというだけでも奇跡だ。しかもやってる音楽は、どストレートなロックンロール。たしかにポップな曲もあることはある。しかし彼らのアティチュードはロックンロールから1ミリもぶれていない。その上で演奏されるポップな曲はどう転んでもロックンロールになってしまう。一度ぼくの知人にボヘミアンズのライブを見てもらったことがある。元CDショップの店長で、ビートルズのファンで洋楽博士のような人だ。曰く「昔は洋楽の匂いをさせた、ボヘミアンズのようなバンドばかりだったのに、どこへ行ってしまったのだろう」。ボヘミアンズとはそういうバンドなのだ。今回は最新作のアルバムツアー・ファイナル。5人中4人のメンバーが書いた多種多様な楽曲で構成された最新アルバムを、彼らはきっちりと再現。最後はいつものようにフルスロットルでロックンロールを鳴らし、2時間以上に及ぶステージを完遂した。パンクのアティチュードを持ちながらもオールドロックにもしっかりアクセスしていくのがボヘミアンズの特徴。この空間だけは90年代のロックンロール・リバイバルから連綿と続く熱が渦巻いている。